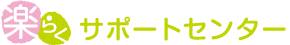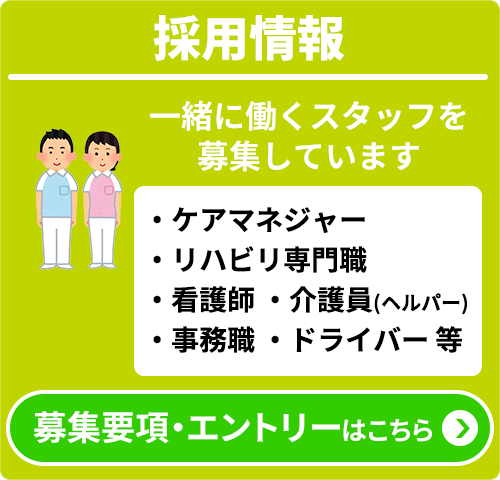4月30日 強度行動障害研修を実施しました
研修開催の背景🌱
プルーンベリーハウスでは、支援現場で直面する 強度行動障害 への理解を深め、「怖い」ではなく 「困っている人を支える」 視点をスタッフ全員で共有するために本研修を企画しました。
講師は当社スタッフで作業療法士の 中川路 です。

そもそも強度行動障害とは?🤔
● 病気そのものではなく、関わり方と環境が生み出す“状態”のことです
● 自傷・他害・破壊行為・睡眠/食事の問題など、これらの行動は ビックリすることもありますが、本人からの SOS サインなんです🚨
● 本人は“大変な思い”を抱え、苦しんでいる当事者 である――ここを理解することが支援の入口といえます👐
講師が伝えた「5 つの核心ポイント」🚩
● “状態”として理解する──ラベルを貼らず背景を想像
行動を“症状”と決めつけず、「今、何に追い込まれているのか?」を想像することが支援のスタートライン。恐れや抑えなきゃという気持ちを一旦脇に置き、“支えるまなざし”で関わる重要性を学びました。
● 本人特性 × 物的・社会的環境の徹底分析🔍
-
-
本人の感覚・認知・身体状態
-
周囲の物的環境(音・光・導線など)
-
関わるスタッフや家族などの社会的環境
これらを要因として整理し、何度も観察と情報共有を重ねて真実に近づく ことが鍵。
-
● 記録を積み重ねる重要性📑
行動が起こるたび「日時・場所・前後の出来事・本人の得た結果」を記録。共通点を抽出し、「その行動で本人は何を得ようとしているのか?」を仮説立て→検証→対応へと落とし込みます。
● 一貫対応はチームプレイ──仕組み化が安心をつくる🤝
対応がバラバラだと本人の不安感は増すばかり。
共通の対応手順・定例ミーティングなどで 一貫した対応 を守り、状態の安定につなげます。
● 事業所の外へ視野を広げ、地域全体で支える🏘️
事業所の中で解決したとはいえ、本人は自宅・学校・地域イベントなど 事業所外でも活動していますし、外部の環境 とも連動しています。
他事業所、学校、行政、住民とネットワークを組み、地域ぐるみで当事者と家族を孤立させない ――これが真の個別支援につながると学びました。
まとめ🌈
● 強度行動障害は 関わりと環境のミスマッチ で起こる“状態”
● 深層分析 → 記録で仮説検証 → チームで一貫対応 → 地域連携 が目指すべき道筋
● 今回学んだ行動の背景を読む力は、すべての対人支援に応用できる!
プルーンベリーハウスは、この学びを現場で実践し、
“その人らしい生活” をスタッフ全員で支えてまいります👐✨